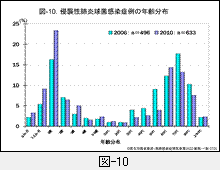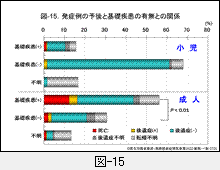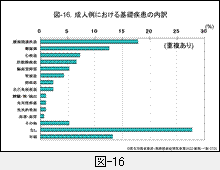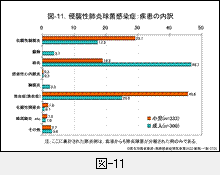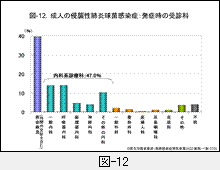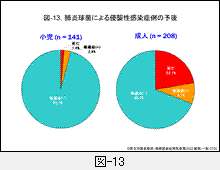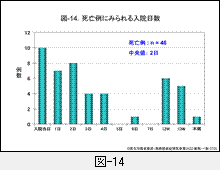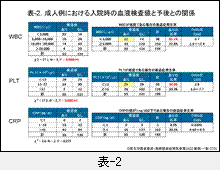発症例の背景解析
発症例はどのような年齢分布をしていますか?
図-10には,肺炎球菌による侵襲性感染症例の年齢分布を示します。2006年(n=496)と2010年(n=633)に収集された全症例の年齢分布です。注目すべきは,小児と成人の2峰性分布を示していることです。
2010年の成績では,小児(19歳以下)のうち1歳児が最も多数を占め,次いで1歳未満と2歳児となっています。発症例は3歳児までに集中していますが,この成績は感染予防と重症化を防ぐことを目的とする小児への肺炎球菌ワクチン接種を考える上で,極めて重要です(ワクチンの項参照)。
成人では30歳から徐々に症例数が増加し,60-70代にピークがみられます。全人口の約4人に1人が65歳以上の高齢者となり,しかも基礎疾患を有する方が増加している現状において,これらの感染症はますます重要です(基礎疾患の有無 : 図-15,図-16参照 )。
ペニシリン系薬が登場して以来,成人の本菌による重症感染症は激減し,”肺炎球菌感染症は子供の病気”とさえいわれ軽視されてきましたが,今や”肺炎球菌による感染症は乳幼児と高齢者の主要な疾患である”といえる状況になっています。
侵襲性感染症として,どのような疾患が多いのですか?
肺炎球菌による疾患を小児と成人とに分け,図-11に示します。これらの成績は菌株をお送りいただく際,個人情報保護に配慮したアンケート用紙[米国疾病対策センター(CDC)のフォーマットに準拠]に,情報を記載していただいたものから集計したものです。
小児では敗血症・菌血症(45.6%)が最も多く,次いで化膿性髄膜炎(29.1%),肺炎(18.9%)でした。この場合の肺炎例は,同時に検査された血液から菌が分離された症例のみを示してあります。そのため症例数は少なくなっています。その他に,感染性心内膜炎(IE),蜂窩織炎,化膿性関節炎等もみられます。
成人でも血液培養検査で菌が分離された肺炎のみを示してありますが,肺炎(46.7%)が最も多く,次いで敗血症(25.0%),化膿性髄膜炎(17.3%)の順でした。小児では報告のみられなかった疾患として,膿胸や胸膜炎などがみられています。
全体としては,化膿性髄膜炎,肺炎,敗血症が侵襲性肺炎球菌感染症の3大疾患であるといえます。
このような重症例は,最初にどのような診療科を受診しておりますか?
図-12は,成人例が発症後に先ずどのような診療科を受診していたのかをまとめた成績です。小児では,小児科受診が大部分のため除いています。
成人では肺炎例が多かったことから,内科系診療科の受診例が多いことはもちろんですが,呼吸器内科だけではなく,一般内科やその他の内科受診例も多くなっています。
注目されるのは,救急外来受診例が40%近くを占めていることです。肺炎球菌感染症は,ひとたび発症しますと急速に病態が進行する感染症であることが判ります。
一方,外科系診療科受診例は少ないのですが,化膿性関節炎を診察する機会が多い場合には,肺炎球菌も起炎菌のひとつとして留意しておく必要があります。
発症例の予後,特に死亡例と後遺症を残した例はどの位あるのでしょうか?
発症例の予後について,小児と成人とに分けた成績を図-13に示します。
先ず,成人発症例において,死亡例が22.1%(n=46),明らかな後遺症を残した例が8.7%(n=18)と極めて多いことが注目されます。その詳細をみますと,60代までの予後不良例には化膿性髄膜炎例が多く,発症3日以内に不幸な転帰をとっています。これに対し,70代以上の予後不良例では,その大半が敗血症や肺炎例でした。
小児では成人例とは違い,死亡例は1.4%(n=2),後遺症を残した例は2.8%(n=4)と少なかったことが特徴です。乳幼児の場合,急な発熱や全身状態の悪化に家族が気づき,早期に小児科医を受診していることが大きいと思われます。
既に季節型に組み込まれましたが,インフルエンザ(H1N1)2009の世界的大流行時に我が国での死亡率が極めて低く,欧米の専門家からは”ミラクル”といわれました。それはひとえに”早期受診と早期診断,そして治療が可能”な我が国の医療制度を反映しているのです。
付け加えておきますと,私どもが2000年から実施している「化膿性髄膜炎全国サーベイランス研究」の髄膜炎例に限った予後調査に関する成績では,成人例の半数が死亡あるいは後遺症を残し,小児でも20%が予後不良となっていました。肺炎球菌感染症は,今でも致死率の最も高い感染症です。
死亡に至る在院日数はどの程度なのでしょうか?
成人での死亡例が多いことから,図-14に死亡46例の入院日数を示します。ほぼ半数の25例が2日以内で死亡と急激な経過を辿っています。特に10例(22%)は受診当日に死亡されていることが注目されます。
確かに肺炎球菌感染症は急速に重篤化しやすいことは事実ですが,成人では高熱があっても自己診断し,症状が重症化してからでないと医療機関を受診しない傾向が強いようです。
基礎疾患の有無は予後にどのような影響を与えていますか?
基礎疾患の有無と予後との関係は図-15に示します。
死亡例と後遺症を残した症例とを合わせて「予後不良例」とし,「基礎疾患あり」群と「基礎疾患なし」群とを比較したものです。下段の成人では,「基礎疾患あり」群(56.1%)は「基礎疾患なし」群(30.7%)に比し,予後不良例が有意に多いことが示されています(P <0.01)。
上段の小児では「基礎疾患あり」は15.5%でしたが,最も多かったのは先天性疾患を持った児でした。予後不良例は「基礎疾患あり」群と「基礎疾患なし」群とでそれぞれ3名ずつ認められています。
基礎疾患として,具体的にはどのようなものが多いのですか?
成人における基礎疾患の内訳は図-16に示してあります。さまざまな生体部位の腫瘍関連疾患(手術後も含む)が最も多く,次いで糖尿病,心疾患,肝胆膵等の疾患,脳血管系疾患,そして腎疾患(透析例を含む)など多岐にわたっています。
入院時の血液検査値と予後との間に関連性はみられるのでしょうか?
表-2は,入院時に測定された成人のWBC,PLT,およびCRP値と予後との関係を調べた成績です。
先ず,「予後不良(死亡+後遺症あり)」群 と 「予後良好(後遺症なし)」群 とに分け,成人における各々の正常値を目安にして検査値を層別し,それに該当する例数を示してあります。
例えば,WBCが5,000/μl 以下の低値である際の予後不良率は 61.1%,5,000/μl以上での予後不良率は21.6%となり,Odds比は5.7で有意な値となっています。
PLTについても同様で,13×104/μl以下の場合の予後不良率は50.0%,それ以上の場合には20.3%となり,その場合のOdds比は3.9で,これも有意な値となっています。
CRPでは3群に層別して両群の比較を行ないましたが,両群ともに10 mg/dl以上の高値を示す例が非常に多く,CRPの診断的価値は非常に高いのですが,成人では予後との関係は認められない結果でした。
結論として,“入院時にWBCが5,000/μl 以下で,PLTも13×104/μl以下と両者が低値を示す場合には,予後は極めて不良である”ということができます。